湯呑み茶碗に比べて、お気に入りの急須を見つけるのは案外難しい。そんな中ひそかな人気を集めているのが、陶芸展での入賞経験が多く、アート作品の制作も行う京焼・清水焼作家の中村譲司さんの急須だ。中村さんの器は、どれも現代の住まいになじむデザインが重視されている。
大学進学を機に、大阪から京都へ。在学中から陶芸展に入選
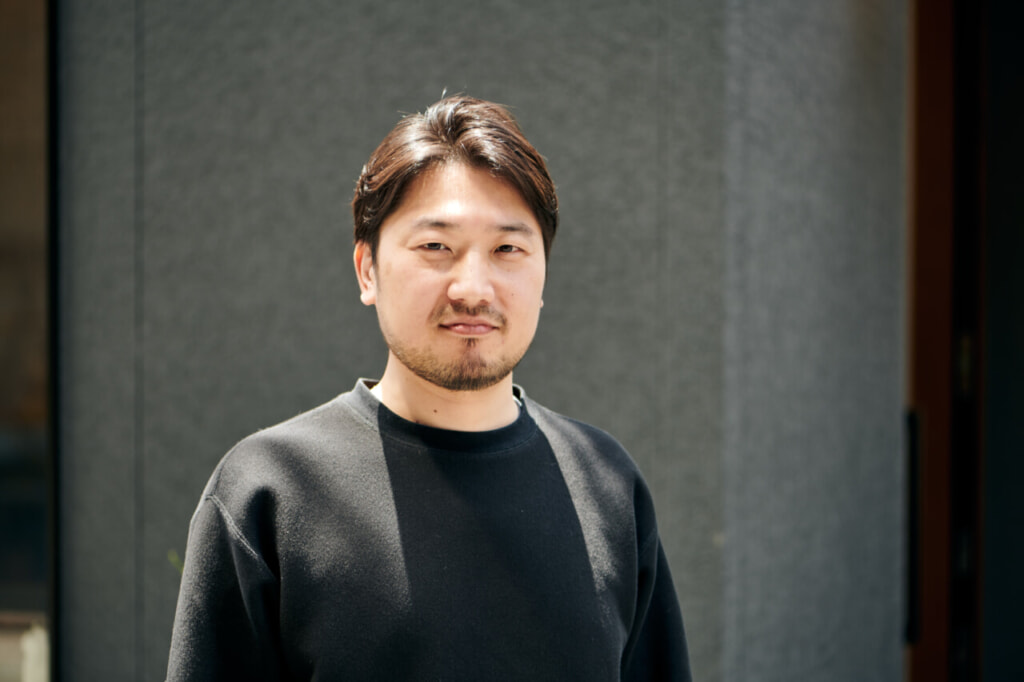
大阪府出身の中村譲司さんは、美術系の高校を卒業後、京都精華大学芸術学部で陶芸を学ぶため、18歳で京都に来た。大学卒業後は京都府宇治市炭山で陶芸家の河島浩三氏・喜信氏のもとに弟子入りし、3年間住み込みで修業に励んだ。器などの実用的な陶芸のノウハウを身につけたこの期間は、自身にとって重要な原点だったと振り返る。
中村さんは大学在学中から、陶芸家の登竜門と位置づけられている朝日陶芸展に入選する実力の持ち主で、修業期間中もいくつかの公募展で入選・入賞を果たしている。本来、弟子入り期間中は展覧会への出品が禁じられているそうだが、空き時間さえあれば制作に打ち込み、作品を作り続ける中村さんの熱心さを見て師匠たちも黙認してくれていたという。
その後、京都市山科区の清水焼団地や母校・精華大学の非常勤講師の仕事と並行して主にアート作品の制作を行っていた期間を経て、中村さんは2012年、清水焼発祥の地としても知られる五条坂に、アート制作とは別に実用品の生産ラインとして稼働する工房「G-studio」を設立。結婚を機に実用品も手がけていこうと決めたのだというが、結果、中村さんの作風の幅はより広がっていくことになる。
京焼・清水焼の中心地に工房を構える

中村さんが工房を構えた京都市東山区にある五条坂界隈は、江戸時代半ば頃から清水坂とともに清水寺の門前として栄えた地域で、参拝客への土産物として焼き物が生産・販売されていた。柳宗悦らとともに民藝運動家として活躍した陶芸家・河井寛次郎が拠点としていたのも五条坂だ。
自分の工房を構えるなら、五条坂周辺で。中村さんは独立前からそう決めていたという。他府県出身で、窯元の跡取りでもない新参者だからこそ、京焼・清水焼の中心地でやる。「五条坂」という選択には、京都の作家として生きていくのだという覚悟が込められていた。
実際、この地を拠点としたことで、多くを学べたという。
周囲にも陶芸家が多く、いろいろな作家とのつながりができただけでなく、ホテルやゲストハウスが建ち並んでいるこのエリアでは、国内外からの観光客と関わる機会も多かった。そこで得た刺激や気づきから、新たな作品が生まれることも。いまや中村さんの代表作となっている茶器も、そうしたきっかけから作られた。
中国人観光客がきっかけで始めた茶器の制作

インバウンドが活況だった頃、世界各地から訪れる観光客の中でも特に目立っていたのが中国人の姿だった。それならと中国茶を淹れる茶器を作ってみたところ、中国人観光客はもちろん日本人にも好評だった。以来、急須は中村さんの代表作のひとつとなった。

とりわけ特徴的なのは、その大きさ。中国茶の急須をほうふつとさせる、一般的な急須よりも一回り近く小ぶりなサイズは、「寒い日の休憩時間に、1杯だけ淹れるのにちょうどいい急須が欲しい」と思っていたことから生まれたそうだ。大きな急須で1杯分を淹れるのは難しく、お茶っ葉も無駄になってしまうので、重宝しているという。
「白翠結晶急須(はくすいけっしょうきゅうす)」「覆黒銀彩急須(ふっこくぎんさいきゅうす)」など、作品には色にちなんだ名前をつけることが多い。デザインにどことなくアジアの雰囲気も感じられるのは、李氏朝鮮時代のものが好きで、自らもコレクションしているという中村さんの好みが反映されているからだ。同時に、蓋がぴったりと閉まるなど手仕事の細やかさにもこだわって、日本の工芸作品の魅力や京焼のエッセンスが感じられるようにしているという。

急須をやる人は少ない。だからからこそ作る意味がある
陶芸家の中でも、湯呑み茶碗に比べて急須を手がける人は、そう多くはないようだ。焼き物の中でもパーツが多く、制作に手間がかかる分、あまり作りたがる人がいないのではないかと中村さんは話す。
だからこそ中村さんは急須に力を入れてきた。最近では、個展や展覧会でも急須の制作を求められることが多いという。
器作りのコンセプトは「建物に合わせて作る」。現代の暮らしに寄り添ったデザインに

洋室のテーブルにもなじみそうな急須をはじめ、現代の居住空間に合わせても違和感のない中村さんの器は、「建物に合わせて作る」というコンセプトで作られている。このコンセプトは、学生時代から暮らしている京都の街で培われた。
「京都には町家の住まいが多いですが、入ってみると中はすっかりリフォームされていて、洋室になっていることも多いです。京都に限ったことではなく、昔ながらの昭和の家をリフォームした家も同じかもしれません。それに、マンション住まいの人も増えています。生活様式が変わったことで住まいのデザインも変化し、それに伴ってインテリアも変わる。器もインテリアの一部なので、変貌を遂げてきた日本の住まいに合う器を作りながら『現代の食卓』を提案していきたいと思っています」

高校時代、進路を選ぶ際にも陶芸と建築で迷ったという中村さんだが、大学で陶芸を始めてから、2つのジャンルは密接につながっていると感じたという。実用的な陶器の多くは建物の中で使われるものだし、街なかのオブジェなども建物とともに風景を形作ることが多いからだ。
リゾートホテルで手がけた、京都の庭園に見立てたパフェのための抹茶碗

【アマン京都 ザ・リビング パビリオン by アマン】「庭パフェ Zen Garden」(2021年 初夏)

住空間だけでなくリゾート施設で使われる器の制作でも、中村さんはその手腕を発揮している。
2021年には京都市北部の自然豊かなエリア、鷹峯(たかがみね)にあるリゾートホテル「アマン京都」にて、新緑の季節に期間限定で登場するデザート用の茶碗を作った。そのデザートとは、ホテル内にある美しい苔庭を一望するレストラン「ザ・リビング パビリオ ンby アマン」で提供する、禅庭に見立てて作られたパフェ。そのパフェを盛り付けるため中村さんが作ったのは、「黒寂幽玄(こくじゃくゆうげん)」という抹茶碗だった。
器の色は、ホテルのデザインともリンクした黒。中村さんの作品でもしばしば用いられる漆黒の釉薬で、鮮やかな緑をしっかりと受け止めるような、揺るぎない強さと深さを感じさせる器を完成させた。
京都人としてのアイデンティティーが育ってきた

2013年には日本画家・上村松園など、日本を代表する作家を多数輩出してきた京都市主催の公募展「京展」でオブジェ「護具〜風神雷神〜」が京展賞を受賞。2018年には、地方の作家の発掘を目的に開催されている「日本陶磁協会奨励賞関西展」では「覆黒銀彩茶器揃(ふっこくぎんさいちゃきそろえ)」が奨励賞を受賞。中村さんはアート作品、実用品の両方で公募展での受賞を果たし、京都の焼き物界の新時代を担う作家のひとりとして活躍中だ。
京都に来てから20年以上が過ぎ、ようやく自分を「京都人」と言ってもいいような気がしてきた、と中村さんは言う。中村さんが作る器や茶道具は「繊細な作風が京都っぽい」としばしば評されるそうだが、陶芸家として独立したばかりの頃は、中村さん本人は自分が京焼・清水焼の作家だと強く意識したことはなかったという。
というのも、信楽焼や有田焼などと違って、京焼・清水焼には技法や原料などにきまりがない。その分「自分の作品が京焼だ」といったアイデンティティーは持ちにくく、中村さん自身の認識としては、作りたいものを作っていただけだった。
しかし五条坂で独立し、たくさんの作家と交流する中で、中村さんは次第に「京都らしさ」を意識するようになった。
「京都に暮らしていると、『この人はいかにも京都の作家だな』と感じる人に出会うことがあります。作品が醸し出すものに共通するものがあり、京都に暮らし、京都の風景や空気、人に触れ、歴史を知ることなどを通して『京都の精神』が染みついて生まれる作品が京焼・清水焼ではないかと思っています。自分が作るものにもそういうものが出てきているように感じてもらえたら嬉しい。」
国内外の陶芸美術館に収蔵されている作品も
京都で過ごした約20年、とりわけ五条坂の地で吸収したものが、中村さんを京都の作家にした。
その手から生み出された、繊細なようでいて揺るぎない強さをたたえた作品は、世界のタイル博物館(愛知県常滑市)、市之倉さかづき美術館(岐阜県多治見市)、ファエンツァ国際陶芸美術館(イタリア)といった陶芸関連の美術館のほか、京都市左京区の寺院・法然院にも収蔵されている。
現代の暮らしに合わせて生み出された中村さんの茶器は、人の動きが活発化し、世界有数の観光地として再始動しだした京都の街で、訪れる人たちに新鮮な感動を与えてくれ、国境も軽やかに越えて行くはずだ。











