“天空の城”として知られる「越前大野城」の城下町・大野市は、名水百選の「御清水」など湧き水の宝庫。
その名水で醸す「野村醤油」は、全国でも数少ない麹から自社製造にこだわる醤油蔵です。
この産地ならではの甘い味わいの醤油、地元産の大豆のみで作る醤油など、
大野の風土が生きた醤油をお楽しみください。
「野村醤油」は明治初期に創業した老舗の醤油蔵。6代目蔵元を務める野村明志さんは、先達が築いてきた蔵の伝統をしっかりと受け継ぎつつ、時代の変化をとらえた柔軟な発想で次々に新商品を開発し、醤油業界に新風を吹き込んでいる。
“名水のまち”で醸す伝統の醤油

大野市は福井県の北東部に位置し、天空の城”として雲海による絶景で全国的な知名度を誇る「越前大野城」の城下町としても知られている。また湧き水の宝庫としても有名で、市街地には環境省が指定する名水百選に選ばれている「御清水」をはじめ、湧水地がいくつもある清らかな水の郷。その中心部に野村醤油の蔵があり、昔から地元のおいしい水で醤油を醸し続けている。
甘くてさらっとした福井の醤油
現在、福井県内には野村醤油をはじめ、20社ほどの醤油メーカーが存在する。福井でつくられる醤油について野村さんは「福井を含む北陸の醤油には特徴があります。それは “甘い”醤油が多いこと。想像にはなりますが昔は甘いものが貴重で、甘い醤油は“おもてなし”のひとつだったのかもしれません」と話す。
ちなみに九州の醤油も甘いが、それがとろみを感じるテクスチャーなのに対し、福井の醤油はさらっとしている。基本的に色の薄いほうが塩分濃度が高いと言われる醤油。福井の醤油の色は濃口醤油と薄口醤油のちょうど中間くらいだ。甘くて程よくしょっぱい“良い塩梅(あんばい)”の醤油として、長く地元の人たちに親しまれてきた。野村醤油の定番商品「大野のおしょうゆ」も、甘くてさらっとした北陸ならではの醤油だ。
麹から作る稀有な蔵
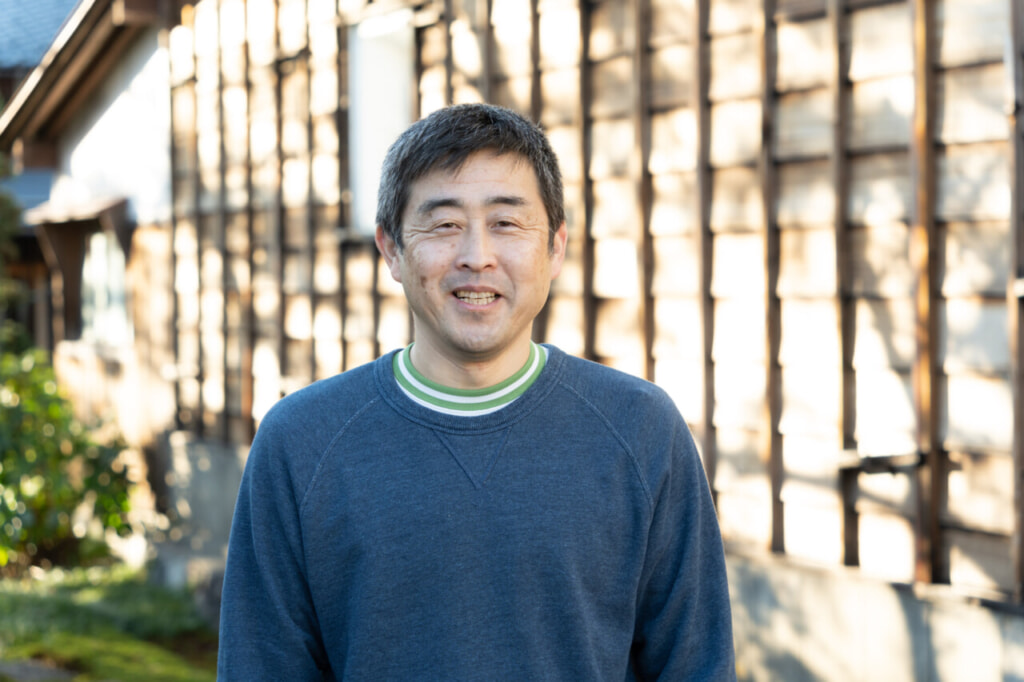
醤油ができるまでの工程は、まず蒸した大豆と炒った小麦を混ぜ、種麹を加えて「麹」を作る。これを塩水と一緒にタンクで仕込んで「もろみ」を作り、攪拌を重ねて発酵・熟成させてから搾ったままのものが「生揚醤油(きあげしょうゆ)」と呼ばれる。この生揚醤油に火入れして瓶詰したものが製品として流通する。生揚醤油に火入れをする際、砂糖や水あめといった糖類やアミノ酸などの調味料を加えると甘い醤油に仕上がる。
かつてはそれぞれの醤油蔵が生揚醤油から製造していたが、高度経済成長期に入ると大量生産・大量消費に対応するため、中小の蔵が組合を作り共同で生揚醤油を製造するケースが増えた。共同で作った生揚醤油を各蔵が仕入れ、火入れや味の調整を行って独自の商品に仕上げる方が設備投資のリスクを抑えることができ、コストも下がるので大手との価格競争を乗り切る上でもメリットがあった。
「全国には1000社近くの醤油メーカーがありますが、うちのように麹から作っている醤油蔵は各都道府県で1、2社しかない」と野村さんが言うように、現在においても野村醤油は麹から自家製にこだわり続けている。
「麹から作る蔵が少なくなったからこそ、自家製の麹が味の個性になる」と話す野村さんは、年間で気温変化の少ない冬場に麹を仕込む。それでも、最も気温が低い1月と春を迎える3月では条件が大きく変わるから、その変化に応じても種麹の量を調整し、醤油に最適と考える麹を作るのだそう。そして、発酵・熟成を進めるための温度調整は一切行わず、大野の四季の温度変化を生かして生揚醤油を作っている。
日本の大豆で醤油づくりを
2013年に和食がユネスコ世界無形文化遺産に登録されて以降、和の料理に欠かせない醤油は、海外からの注目も高い。しかし、醤油の原材料である「大豆」の収穫はその年や地域によってばらつきが大きく、栽培する農家の数も減少しており、飼料用を含む全体の自給率はわずか6%。食用だけでも20%程度にとどまるのが現状だ。
「大豆の自給率の低さは、醤油業界が抱える大きな課題です。うちの蔵でも定番商品に使っているのはインド産の大豆がメインですが、国産の大豆を使った高単価の醤油づくりにもチャレンジしています」と野村さんは話す。
伝統製法を「個性」に
野村醤油の伝統を受け継いだ先代のもとで専務を務めていた野村さんは2007年、地元で青大豆を育てる農家からうちの大豆を醤油に使ってもらえないかと相談を受け、「青豆しょうゆ」というオリジナル商品を開発した。安価な醤油は粉砕した大豆で仕込むので早く作れるが、大豆を丸のまま仕込む「青豆しょうゆ」は発酵に時間がかかる。また、仕込みの際、温度を上げることで発酵は早く進むが、温度調整をしない野村醤油の蔵では、夏の暑い時期に発酵・熟成がゆっくりと進み、仕込みは2年がかりになる。希少な青大豆は仕入れ値も高く、製造に時間がかかるため販売価格は定番商品の約7〜8倍にもなるが、現在まで続くロングラン商品となっている。同商品は、火入れの際に糖類もアミノ酸も加えないので、青豆本来の特徴である自然な甘みが活きる。昨今の醤油業界で高く評価されているアミノ酸が多い醤油とはちがうが、今は、昔ながらの製法が個性になる時代。幸運なことに、野村醤油は昔からの製法を絶やさずに受け継いできた。それこそが、かけがえのない財産だと、野村さんは言う。
製造技術の進歩により、手頃な価格で手に入る大手メーカーの醤油は食卓にあって当たり前の調味料となった。逆に考えれば、地域ごとに存在する小規模な醤油蔵の商品を目にする機会は減っているということ。
それゆえ、蔵ごとに異なった醤油の個性を比較するということが、あまり現在ではなくなってしまった。青豆しょうゆは、その “昔の当たり前” に戻ることを付加価値にした商品だ。しかし原点回帰だけでは時代の変化に対応できないという危機感も持ち合わせていた野村さんは、新しい取り組みも進めていた。
新商品で醤油の未来をひらく

「ちょうど私が生まれた1973年をピークに、醤油の出荷量は減少を続けています」と野村さんが言うように、ひとり当たりの年間消費量も1973年から2021年の約50年でおおよそ半分まで減少した。「極端な言い方にはなりますが、うちの定番商品のような糖類やアミノ酸を加える醤油はこれ以上伸びることはない」と野村さんは断言する。食の多様化、単身世帯の増加、外食や中食の台頭といった時代変化の中で、家庭で下ごしらえが必要な調理をする機会は大きく減少。醤油は卓上に置いてかけるだけ、という使い方が圧倒的に増えた。そんな中で野村さんが活路を見出したのは、何にでも合う醤油ではなく、「この料理にはこの醤油」というニッチな新商品の開発だった。
福井名物専用の醤油ダレを開発

新商品は認知されるまでに時間がかかる。しかも野村醤油のように小さな蔵は、新商品を大々的にPRしたり、発売のタイミングに合わせてスーパーなど小売店の棚を確保するのは難しい。そこで野村醤油は、地域で知られている名物料理の味わいをさらにアップするような専用の醤油ダレを作ることに取り組み、蔵としての認知度を向上させる施策に打って出る。
その先駆けとなったのが、2003年に先代が福井県内のほかの醤油蔵と共同で開発し商品化した、福井名物「おろしそば」の専用つゆ。醤油をベースに甘味を抑え、そばの香りやおろしの辛味が活きるような味わいに仕上げた。
その後、2009年に先代から蔵を継いだ野村さんが福井名物であるソースカツ丼から着想を得た「醤油カツ丼」を考案し、福井県内50以上の飲食店でメニュー化させることに成功。自ら普及させた醤油カツ丼専用の「アッサリたれ 醤油カツ丼」の商品化を皮切りに、新商品開発を加速させていく。
醤油蔵がこのようなつゆやたれを開発できたのは、父である先代が野村さんがまだ幼い頃から研究を重ねてきたから。付き合いのあった製麺所からそばつゆを作れないかと相談を受けた先代は手鍋での試作から始め、大手食品メーカー出身の専門家にコンサルを依頼。レシピ開発や必要な設備、衛生管理などの助言を受けながら開発に取り組んだ。そして何より、つゆやたれの主たる原料である「醤油」がすぐ手元にあるのが大きかったと野村さんは言う。「これが食品メーカーさんだと醤油を仕入れなくてはなりませんが、うちにはそれこそ醤油だけなら売るほどあります。それに醤油は瓶詰めしてからも賞味期限が1年以上あるので、出荷が減って増えた在庫をつゆやたれに活用して新しい価値を生み出せるのも強みです」
大野名物を生かした醤油ダレも

2014年には、地元である大野市に根付いた名産に目を向けた「焼魚にあうおしょうゆ」を発売。大野には夏至から数えて11日目の「半夏生(はんげしょう)」に丸焼きのサバを食べる風習があり、そのサバに合うようにと旨味を強くした商品だ。また、2017年には「里芋ころ煮だし」と「舞茸ポン酢」を開発。里芋のころ煮だしは、500gの里芋に加えて煮るだけで、水を使わず簡単に大野の郷土料理「里芋のころ煮」を作れる簡単調味料。一方、舞茸ポン酢は、大野名産の「九頭竜(くずりゅう)まいたけ」を加工するメーカーから大量に出る煮汁を活用し、舞茸の旨味たっぷりで酸味がまろやかなポン酢に仕上げたアイデア商品だ。
消費者との関わりを活発に

福井名物に特化した新しい醤油商品の開発に手応えを得た野村さんは、福井の醤油を身近に感じてもらうための取り組みも開始。2016年には野村醤油の敷地内に「体験蔵 重右ェ門(じゅうえもん)」をオープンした。熟成中のもろみを櫂(かい)棒を使ってかき混ぜる「櫂入れ」を体験したり、熟成した「諸味」を搾る様子を目の前で見られる施設で、子どもから大人まで幅広い層に伝統的な醤油づくりを伝えることができる。
2019年には、インターネット通販を手掛ける地元の会社と共同で「名前のない生醤油」を発売した。スーパーなどに並ぶ一般的な醤油は火入れして発酵をとめたもので、味に丸みがあり香ばしさを感じる。また、「生醤油」と書かれていても火入れはしていないが発酵を進める菌を取り除いている場合が多い。一方、「名前のない生醤油」は搾ってから火入れも菌も取り除いていない「生揚醤油」を瓶詰めする。生醤油は味が濃厚で、フレッシュな酸味があるのが特徴だ。「名前のない生醤油」の材料には、大野在来品種の「大だるま」という大豆、福井県産の小麦「ふくこむぎ」、そして大野の水を使用。これも大豆を丸のまま仕込み、温度調整をせずに発酵・熟成させるので、完成までに2年を要する。そこで、発売の2年前から福井市のそば店の協力を得て「生醤油倶楽部(きじょうゆくらぶ)」というコミュニティをつくり、料理への生醤油の使い方や、醤油の伝統的な製法、原材料へのこだわりをイベントやSNSを通して発信を続けた。併せてクラウドファンディングにも挑戦し、目標金額を大きく上回った。まさに、“モノ”だけでなく“ヒト”や“コト”も動かすプロジェクトとなった。
醤油の魅力を未来に
小さな蔵の挑戦の数々は知名度を着実に高め、次第に県外の有名シェフや高級ブランドからコラボの話が舞い込むようになった。2020年、北陸・東北・北海道新幹線のグランクラスの軽食メニューに使う醤油として野村醤油の商品が採用された。監修したのは、ミシュランで2つ星を獲得した「日本料理 一凛」の橋本幹造シェフ。シェフから野村さんに「日本食再発見」をテーマにした献立に合う醤油が欲しいとのオファーがあり、「名前のない生醤油」を特別に火入れして提供した。
2021年には、チョコレートの高級ブランド「ゴディバ」が展開する「GODIVA café Tokyo」にて、福井県とのコラボで提供した「ビーガンサラダヌードル」の食材として舞茸ぽん酢が採用された。こうして次々とフィールドを広げていく野村醤油。
蔵元の野村さんは「これからも醤油作りの原点を大切にしながら、“いま求められる”醤油を追求していきます」と語る。
醤油は蔵ごとに個性があり、料理によって使い分けることでより味わいが引き立つ。この“古くて新しい”醤油の魅力を、野村醤油はこれからも伝えていく。

「野村醤油」が創業した明治初期と現代では、醤油造りを取り巻く状況は大きく異なります。大豆は輸入に頼るようになり、麹造りから醤油を作るメーカーはわずかになりました。伝統を守る蔵の一つとして、「野村醤油」が作り出す味はどうあるべきかを日々模索しています。また、美味しいが当たり前になった今、プラスアルファの魅力も創造してまいります。











