1893年に京都で創業の和菓子屋。
京菓子の魅力は味覚だけでなく、色や形から目で、菓子の名前から耳でも楽しめること。
昔ながらの伝統や格式を守りながら革新的な姿勢も忘れず、
魅力的な京菓子を作り続けています。
和菓子の職人が込める思い

創業は1893年という歴史ある和菓子屋。
当初は、寺社や茶人のために干菓子や蒸菓子などを作っていたが、戦後に発売した「野菜煎餅」が、「末富」を有名にした。野菜煎餅とは、いわゆる玉子煎餅に、巨椋池のレンコンや堀川ゴボウ、鞍馬の木の芽など、京野菜を薄くして混ぜて焼いた煎餅だ。子どものお菓子であるはずの玉子煎餅が、上品で大人にも喜ばれる煎餅へと変身した。もちろん生菓子の美味しさにも定評がある。
昔から親しまれてきた「末富ブルー」

「末富ブルー」の包装紙は、末富の代名詞の1つ。
末富のお菓子は“お使いもの”としても大変人気があるが、その理由の1つとして、美しい包装紙が挙げられる。透明感と目を引きつける鮮やかさが同居し、洋風ではなく和の趣を感じさせる青色は、「末富ブルー」と呼ばれるこだわりの色目。戦後、末富の2代目が日本画の画伯に新しい包装紙の意匠を依頼し、議論を重ね試行錯誤を繰り返して生み出されたもの。派手過ぎず斬新で、すっきりとした上品な印象を与えるこだわりの包装紙が、末富の和菓子でつながった人々の気分をさらに盛り上げてくれる。

今回中田は、生菓子作りにチャレンジ。感動したのは、完成したお菓子の1つ1つに「Hide」という焼きゴテを押してくれたこと。しかし、1個ずつ手作業で作り上げるため、綺麗な和菓子に仕上げるには、長年研鑽を積んだ職人の技が必要である。末富のお菓子は“お土産”としても喜ばれるが、それは包装紙にもこだわっているから。透き通るような淡い青、「末富ブルー」と呼ばれるこの包装紙の美しさが、食べる前から気分を盛り上げてくれる。プロならではの心配りだろう。
京都ならではの菓子を、食べる人、買う人を思って作る。老舗というブランドにあぐらをかかない、熱い想いが伝わってきた。
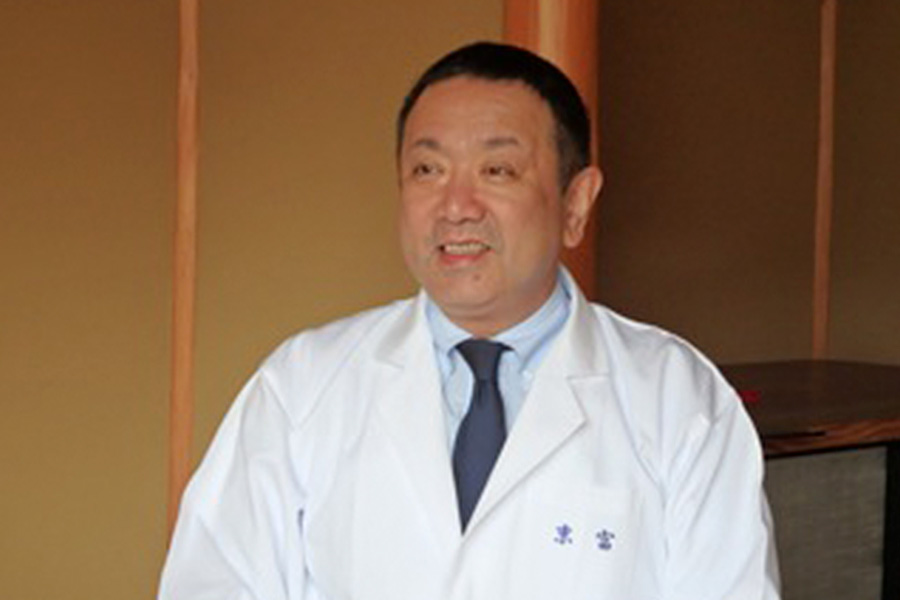
あらゆることに心を動かし、日本文化の一端を担ってきた京都の地で育まれた京菓子には、粋な遊び心がいっぱいです。末富の和菓子を通じて、京都ならではの「夢と楽しさ」をお届けすることを目指して、今までもこれからも研鑽を積んでいきます。











