サビのような風合いを持つ陶器。

気鋭の若き陶芸家として注目されている井口大輔さんの作品の最大の特徴は、サビのような風合いの肌だ。中田も一目見て「この器、パッと見たら鉄がサビたもののように見えますよね。でも陶器なんですよね…」とつぶやく。
「自分の作品を銹陶(しゅうとう)って呼んでるんです。まさにサビた陶器という意味。もともとこういう風化したようなものが好きなんですね。岩にコケがこびりついたような感じがすごく好きだったんです。だからそれを陶芸で表現したいなって思って」
ただし、この風合いを出すまでには長い歳月がかかったという。
風合いを作りだす。

サビの風合いを出すためには、整形して素焼きをしたあとに、もみの灰を表面に塗る。
そして釜で焼きあげたあとにワイヤーブラシで磨くという技法をとる。このもみの灰に行き着くまでが大変だったという。石や木などいろいろな素材を試してみた中で、もみの灰にいきついたのだそうだ。
木の灰だと釜の熱で溶けてしまいビードロのようにつやつやになってしまう。けれどももみの灰は高温でも溶けないので、薄い膜ができる。そこまで削り出していくとサビの風合いを持った肌ができるのだ。しかも現在は、もみの灰に何を入れるかによって、肌の表情を変えることもできるようになったという。
てびねりの形にこだわる。
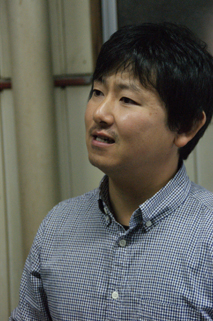
井口さんの作品のもうひとつの特徴が独特なフォルムだ。ゆったりと丸みの帯びた温かみがあると思えば、シャープな鋭さがある。その融合が独特の印象を与えるのだ。これは手びねりだからこそ出せる姿だという。
「微妙にゆがんでいる。このゆらぎがあるのが心地いいと思うんです。これは手びねりじゃないとできないんです」
中田が工芸作家の人たちによくする質問が「使える」ということをどう捉えるかということ。これは中田が工芸品そのものの美に加えて、どう使ったら美しいかという考えをするからだ。今回もその質問をした。
井口さんは、「もちろん器ですから、使ってもらわなくちゃいけないと思うんですけど」といって、こう答えてくれた。
「ただ、使いやすいものって考えて作ってしまうと、やっぱりつまらない形になってしまうんですよ。だからどう使ってくれるかっていうのは、逆に楽しみなんです」











