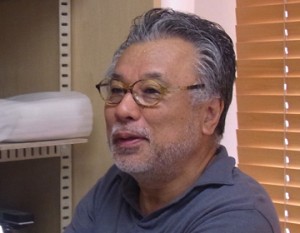目次
熊本の陶磁器
近代熊本における窯業のはじまりは、文禄・慶長の役の際に、加藤清正・細川三斎らが朝鮮から陶工を伴ったことであるといわれている。県内の各地域に焼き物が広がっていくものの、明治に入り、藩の保護がなくなるとともに他県からの安価な製品が流入、廃業が相次ぐ。現在、熊本県下に残っているのは高田焼・小代焼・一勝地焼・水の平焼・丸尾焼・広山焼・高浜焼・内田皿山焼といった陶磁器だ。
世界的な陶磁器原料の天草陶石
天草には、世界的な陶磁器原料の天草陶石が産出する。陶石を砕きその粉を練り合わせ焼いた物が磁器であり、有田焼に使用される陶石の90%はこの天草陶石ということだ。高い強度で製品は硬く、仕上がりの色に濁りがなくて美しいのが特徴といわれている。

いつの時代にも受け継がれる高浜焼
高浜焼きは、1762年、上田家六代目の伝五右衛門が肥前の陶工山道喜衛門を招き高浜に窯を築いたのが始まりで、当時の「染付錦手焼」はオランダへも輸出されていた。七代目宜珍の頃は染付にも高度な技法が施され「高浜焼」が精彩を放った充実期を迎え、その後も焼き継がれてきたが明治中期に中断、60年余りの後の昭和27年に再興した。
こうした歴史を経て、現代の生活様式に調和する、白くて薄く透明な「高浜焼」となり、広く愛用されている。また、宜珍が瀬戸焼の磁祖加藤民吉に錦手の秘法を伝授したということも有名な話である。