吹きガラスの味のある美しさに魅了され、伝統の技法で毎日の食卓にのぼる器を作るガラス作家・三浦侑子さん。使い勝手を考えた器は手にすると安定感があり、食卓で凛とした佇まいを見せる。和食や洋食といった料理のジャンルや場面にかかわらず、“日々使える器”をコンセプトに、暮らしに溶け込むガラス作品を作っている。
自然豊かな岡山県北の地に移住

吹きガラスの作家、三浦侑子さんの工房『Bamboo Glass』は、岡山県苫田郡(とまだぐん)鏡野町の静かな山間の地にある。岡山市内からクルマで約1時間半、鳥取県境まで15分ほどの距離。近くには岡山県美作地方を代表する奥津温泉や名勝地の奥津渓があり、四季を通じて豊かな自然に恵まれるエリアだ。三浦さんはこの地で2014年、工房を始動させた。
毎日の食卓にのぼる器を制作
三浦さんが作る器は、無色クリアや淡いグレーのかかったコップやワイングラス、お皿、ボウルなど。「吹きガラスは2000年以上の歴史がある技法です。私は昔の人が使っていた器のフォルムにとても惹かれるので、その歴史をしっかりと勉強して、現代の人にとっての使いやすさを考えながら自分らしいデザインに挑戦しています」
大学在学中、吹きガラスと出合う

三浦さんは大阪府生まれ。京都造形芸術大学在学中に陶芸や木工など様々な工芸にふれ、そのなかでもっとも惹かれたのがガラス工芸だった。さらに追求したくなり、京都市にあった工房「Glass Studio Aaty」の教室で吹きガラスの経験を積み重ねた。数あるガラス成形の技法から「吹きガラス」を選んだのは、じっとしているのが得意ではないから、と笑う。
だからこそ、体を動かしながら作る吹きガラスは性に合ったのだろう。実際にやってみると、そればかりでなく溶けたガラスの動きが面白く「吹きガラスについてもっと知りたい」「やわらかい状態のガラスを扱いたい」と考えるようになっていった。
吹きガラスは、高温溶融したガラスを「吹き竿」となる鉄管に巻き取り、空気を吹き込んで風船のように膨らませて成形する。型にはめ込んで成形するよりも薄いガラスを作ることが可能で、その技法は古代ローマ時代からほとんど変わっていないといわれる。
ガラスを仕事にするために勉強を続けようと、大学卒業後は富山ガラス造形研究所造形科に進んだ。2年間、ガラスの基礎となる理論、技法や必要なデッサンから、作家として独立するノウハウまで学んだのち、静岡県の『磐田市新造形創造館』でガラス工房のスタッフとして5年間勤務。同じスタッフとして働いていた夫の和さんが岡山県苫田郡鏡野町の『妖精の森ガラス美術館』に就職したことを機に、この地に移り住んだ。
同じことを繰り返しても、同じものはできない

現在は住まいの一角に工房を構え、ひとりで制作している。工房には作る器のサイズに合わせて自作した2つの炉が並ぶ。作業用の炉の温度は約1000℃。ガラスを溶かして貯めておく炉の作業中の温度は約1180℃。こちらはガラスの気泡などを除去するため24時間稼働させ、翌朝すぐに作業できる状態にしている。ふたつの炉が発する熱に包まれながら、コップであれば朝から晩まで20〜30個を作り続ける。「同じことをひたすら毎日、繰り返しても飽きない。それが不思議です。同じものを作っているつもりなのに出来上がったものは一つひとつがどこか違う。だからでしょうか」

古いガラスを見て学び、自身の創作では洗いやすい形状や簡単には割れない厚みなどを工夫して現在のスタイルにたどり着いた。色合いは汚れのつきにくい無色クリアが中心で、ほかに古いグラスの持つ雰囲気を出そうと、ガラスに鉄や銅を微量、混ぜ合わせてグレーがかった色味の器も作っている。いずれも食卓で主張せず、馴染みやすい色合いだ。
好きなグラスのひとつに、20世紀のフランスの大衆食堂で使われていた脚付きのグラスがある。いわゆる「ビストログラス」と呼ばれるもので、ある程度大雑把に扱える丈夫なグラスだ。「このグラスのように手に取りやすく、素朴な日常性のあるものを作りたい」と話す。
創作を始めた当初は自分の作品を知ってもらうため、全国のクラフトフェアに出展した。長野県松本市の「クラフトフェアまつもと」や、静岡県静岡市の「ARTS&CRAFT 静岡手創り市」、岡山県倉敷市の「フィールドオブクラフト倉敷」などでお客さんと話をして自分の作る器への反応を知った。陶磁器と並んでも干渉せず、洋食にも和食にも使えるガラス器は意外と少ないことを知り、「食卓に馴染むガラス」というテーマが確固としたものとなった。口コミで取引先は徐々に増えていった。
仕事と暮らしがつながる環境
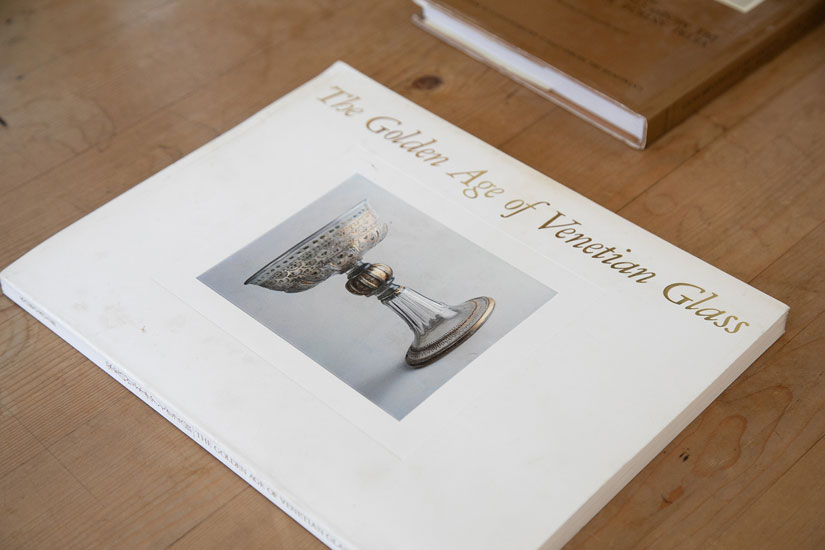
三浦さんは、古書市などで集めた古いガラス器に関する書物を夜な夜な眺め、制作のモチベーションにしている。「例えば16世紀のベネチアングラスなど、写真であってもずっと見ていると当時の職人が頑張って作ってきたんだなって感動するんです。道具の跡など作業の痕跡を見つけたりしながら、どんなふうに作っていたかを自分なりに考えてみるのが楽しくて」

山のふもとで気兼ねなく、のびのびと仕事ができる現在の環境は、仕事と日常がうまくつながっているという。例えば朝、家の周囲の落ち葉を掃き集めることも仕事に向かうまでの大切なリフレッシュ法のひとつ。自然を感じながらさっぱりとした気分で工房に入ることができる。「これから先も今の生活を続けたいです。機織りをして生活をつないできた女性のように、山の中でコツコツと毎日、作っているイメージなんです。仕事は生活の一部ですから」と笑う。
最近になって7月半ばから8月の気温の高い時期は炉の火を落とし、今までは持てなかった自由な時間を使って博物館でガラス器を見たり、ガラスの資料を集める時間にあてたいと考えている。資料を見ているだけではわからないこともあるはずと考える。
この地に移住して以降は子育てに専念し、アルバイトをしていた時期があった。それでも頭のどこかでいつも「また吹きガラスの制作をやる」と考えていた。自身の創作意欲を疑ったことがない点に三浦さんの強さが現れる。日々の生活からインスピレーションを見つけ出し、創作に向かえることが三浦さんにとって何よりの喜びなのだ。











