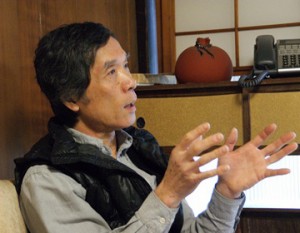千葉県の観光地、房総半島の立ち寄りスポットとして人気を博してきた小泉酒造が、十四代目の小泉文章(ふみあき)さんの代になってから、吟醸酒や純米吟醸酒クラスの酒質を大きく向上させた。自社田での米栽培、千葉県産米の可能性を引き出した醸造など、十四代目の活躍が見逃せない。
磨き続けた技術力と特定名称酒への挑戦

房総半島のなかでも東京湾に面した内房地域を代表する酒蔵である小泉酒造。1996年に前当主が酒蔵の隣に建てた直売所「ソムリエハウス 酒匠(さかしょう)の館」は最盛期で年間10万人以上が訪れた実績もある、ツアーバス定番の立ち寄り先になっている。
だが、そんな観光蔵のイメージとは裏腹に、十四代目の現当主である小泉文章さんは、普通酒が多かったこれまでのラインナップを吟醸酒や純米酒といった特定名称酒への切り替えを進めたことで、より高い技術力を備えた酒が主力となった。「うちの銘柄『東魁盛(とうかいざかり)』や『東魁(とうかい)』という名前が持つごついイメージと、今推している商品の繊細な酒質との間にギャップがあって悩んでいます」と、小泉さんは苦笑いする。
代々技術を磨き続けた全国新酒鑑評会受賞の常連蔵

鹿野山(かのうざん)の山麓に広がる、里山の風景のなかに佇む小泉酒造。創業は1793年(寛政5年)。敷地のそばを東京湾に注ぐ湊川が流れているが、江戸時代にはこの水運を利用して酒が江戸に運ばれたという。
小泉酒造では小泉さんを含め、製造にあたるのは基本的に三名で、年間生産量は約250石(1石=約180リットル)。小規模な酒蔵だが、酒質向上への積極的な姿勢は代々受け継がれてきた。例えば、昭和初期から冷蔵庫を導入し、温度管理を行いながら吟醸酒造りに取り組み始めた。父親である先代にいたっては自ら杜氏となり、経営者でありながら酒造りの責任者を務める蔵元杜氏として製造現場で指揮をとる。品評会への出品を通じてフィードバックを得ながら品質を高めることに尽力した。そして、現当主の小泉さんも杜氏として技術を磨いている。
こうした、酒の品質と技術力を大切にする蔵の姿勢はしっかりと受賞歴に反映されている。象徴的なのは、明治時代からの長い歴史を持ち、国内で最も権威のある大会とされる「全国新酒鑑評会」の金賞受賞の常連蔵であることだ。令和6年(酒造年度令和5年)も「大吟醸 東魁盛」が金賞を受賞。これで13年間連続の入賞で、金賞受賞は通算21回にのぼる。兵庫県産山田錦を55%まで磨いた「東魁盛 純米吟醸 なのはな」は、全国の技術指導者や蔵元、有識者が審査員を務め日本酒のトレンドを牽引する「SAKE COMPETITION2024」で特別賞JAL空飛ぶSAKE賞を受賞した。
ゼロから始めた十四代目のチャレンジ

小泉さんは大学で物理を専攻。半導体関連の会社に入社し「醸造も酵母も何も知らない状態」だったという。だが2009年、父親が体調を崩したことをきっかけに、蔵に戻ることを決めた。当時はまだ普通酒の製造が主軸であったが、その販売量が落ち込んできていた時期でもあり、自らの技術力のなさと販売面での苦戦をしいられる。まさに「ゼロからのスタート」だった。
「教科書は片っ端から読んで、酒造りをやっている人に聞いて、そして実践するの繰り返しでしたね」と振り返る小泉さん。日本三大杜氏に数えられる酒造り集団「南部杜氏」に学び、今では南部杜氏として製造現場を指揮するまでになった。
一方、酒蔵の設備更新にも着手。吸水率を調整できる洗米機から始まり、冷却装置付きの仕込み容器であるサーマルタンク、冷蔵コンテナ、パストライザーと呼ばれる効率的に火入れができる機械を順次導入していく。特に、温暖な千葉県においては冷蔵設備が重要だ。昨今の高温が続く気候も踏まえると「冷蔵設備なしでまともに造れるのは12月から2月ぐらいまで」という。
こうした品質管理や作業の効率化に加え、技術力を磨くことに情熱を燃やした代々続くその姿勢を受け継いだことで、酒質の向上に貢献。純米吟醸クラスを中心に、特定名称酒のラインナップに厚みを持たせることができるようになった。小泉さんが蔵に戻った当初は千葉県外での酒販店との取引がほぼない状態だったが、現在は千葉県内はもちろん、日本酒の書籍監修や品評会運営にも携わり、トップクラスのホテルやレストランなどから厚い信頼を得る「はせがわ酒店」など、東京の酒販店との取引が実現している。
自社田で栽培した米で醸す

小泉さんが先代から受け継いだのは、技術を磨き続ける姿勢だけではない。「酒造りは米作りから」と、原料米が栽培される現場にまで想いを寄せた先代の意志を継ぎ、従業員とともに自社田で米の栽培も行なっている。
「素直に小泉酒造らしさが出た酒かもしれない」という「東魁盛 特別純米 自社田 五百万石」。名前の通り、自社田で栽培した酒造好適米、五百万石で仕込んだ酒である。酒蔵の近所にある自社田は約1.6ヘクタールの広さ。この自社田で収穫した米を小泉酒造で醸す酒の一部に活用している。この田んぼで栽培している米は五百万石だった。「だった」と過去形なのは、2024年の田植えから、栽培する米の品種を切り替えたからである。
千葉県生まれの米で未知なる挑戦へ

2024年は千葉県が開発した酒造好適米「総の舞(ふさのまい)」の田植えを行なった。五百万石の種籾を入手しにくくなったのが品種を変えた直接的な理由とはいえ、まだ自社で仕込んだ実績のない総の舞を栽培するのは挑戦的なことである。だが、小泉さんの中で、千葉県産米の可能性への期待は大きなものだった。その裏付けとなるのが「純米吟醸 東魁 ゆめかなえ」という酒の存在である。
「ゆめかなえ」は千葉県が開発した低グルテリンの米品種。グルリテンとはタンパク質の一種のことで、その含有量が低い低グルテリン米で仕込むとライチのような吟醸香を帯びるのが大きな特徴だ。「ワイン好きな方や日本酒ビギナーにもおすすめできる」と、100%ゆめかなえで造ったこの酒は、今や小泉酒造の定番酒の一つになっている。
小泉酒造では、もちろん千葉県外から酒造好適米である山田錦を仕入れて使うこともあるが「こうした千葉県の米の個性を引き出す面白さもある」と小泉さんは千葉県産の米で仕込むことの意義を強調する。果たして自社田の総の舞からどのような酒が誕生するのか。「自社田 五百万石」が一定の評価を得ていただけに、今から期待が膨らむ。
これからも千葉県産米の可能性を探り続けたいという小泉さん。加えて、自社田の耕作面積も増やしていきたいという。それは「地域の高齢化で耕せない田んぼが増えてきている」から。これまで地域の人たちにも原料米を栽培してきてもらっていた。その恩返しをしたいとの想いが米作りへ気持ちを向かわせているのだ。絶え間ない技術力の研鑽と郷土への愛情が、今後も千葉・内房の風土を醸した酒を生み出させていくだろう。