吉田松陰や伊藤博文ら幕末の志士が学んだ「松下村塾」で有名な歴史深い町、山口県萩市。大河ドラマなどでも度々舞台となり、古都のイメージが根強いこの町に、陶芸家として注目を集める若者がいる。34歳で萩焼の宗家である坂高麗佐衛門(さかこうらいざえもん)を襲名した坂悠太さんだ。約400年続く萩焼の名跡を継承した若き陶芸家が守り継ぐ、萩焼の魅力とその未来とは。
国内有数の歴史的城下街・山口県・萩

そんな人気観光地に古くから伝わる伝統工芸品の萩焼。その起源は、慶長9年(1604年)まで遡る。萩藩初代藩主の毛利輝元が広島から萩に城を移し入府。かねてより帯同していた朝鮮人陶工の李勺光・李敬(りしゃっこう・りけい)兄弟が毛利氏の命を受け、萩城下松本村(現・萩市椿東)に萩藩御用窯として開窯したことがはじまりとされる。その後、兄弟は、それぞれ日本に帰化し、兄の李勺光は長門の地で山村家(後の坂倉家名)を名乗り、弟の李敬は寛永2年(1625年)に二代藩主綱広より「坂高麗左衛門」の名を授かる。この李敬の末裔にあたるのが、坂窯を守る坂家である。
抹茶椀としての萩焼の魅力
ちなみに萩焼という呼び方が全国に浸透するのは意外にも明治時代以降で、それまでは城下街の地名をとって「松本焼」と称されていた。戦国時代の茶人、千利休が侘茶(わびちゃ)の表現として見出し、抹茶碗として広く普及してきた萩焼。その特徴は、萩周辺で採れる「大道土(だいどうつち)」を胎土とした土味のある素朴さ。砂や小石を含む砂礫が多い大道土を、過剰に焼き締まらないよう短時間且つ、高温で焼き上げることで軽い質感で、水や油の染み込みなど、経年での表情の変化が楽しめる。鉄分の多い「見島土(みしまつち)」、軽さのある白土「金峯土(みたけつち)」を大道土に混ぜることによって生まれる土本来の荒々しさと、きめの細かさの融合がもたらすテクスチャーも魅力だ。
萩焼の抹茶椀は、装飾を極力排し、釉(うわぐすり)のみで表面を仕上げることが多く、抹茶本来の色の美しさとの対比により、茶を存分に引き立てるため“詫びさび”を珍重する茶の道で長年高い評価と人気を得てきた所以だ。
2022年6月、34歳で名跡を襲名した若き当代
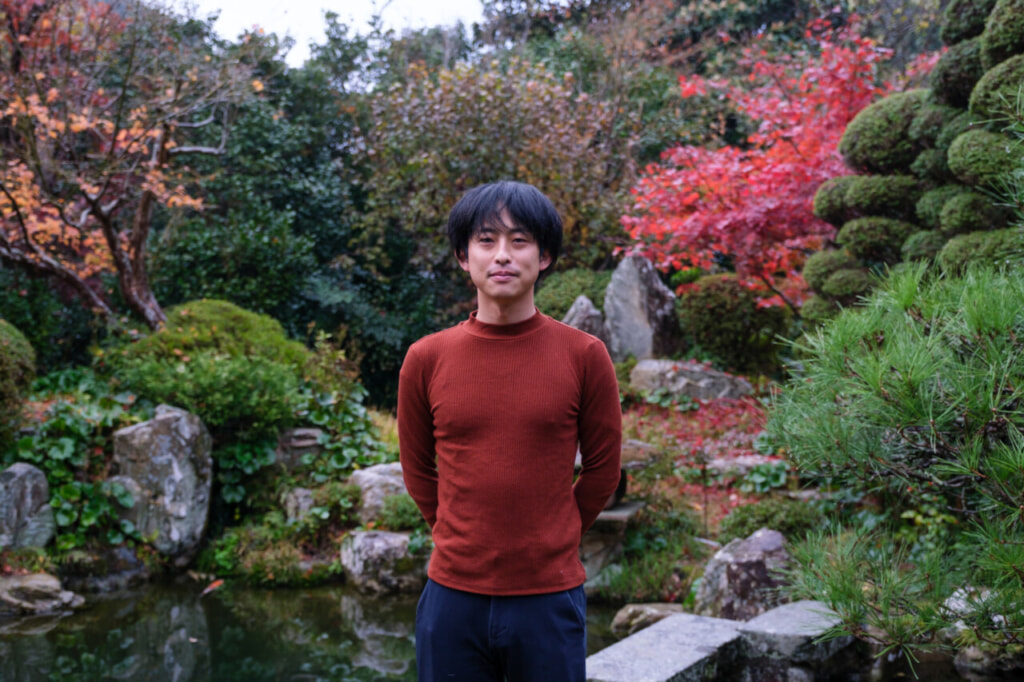
もともと、陶芸に関わる家系だという認識こそあったが、高校生まで陶芸に触れずに育った。坂さんにとって坂窯は単に祖父母の家という感覚だったそうだ。ところが、十二世を継いでいた伯父(母の兄)の急逝により環境が一変。後継者もいないことから、名跡が7年間空位となってしまう事態に、母親の純子さんと共に名門を継ぐことを決め、陶芸家を目指した。
重責を担うプレッシャーがなかったかといえば、もちろん多少なりとはあった。しかし、「昔から歴史の分野には大変興味があり、歴史や伝承を支える当事者になれるのだったら、それは面白いと思った」とも語る。
そんな楽天的な考え方に相反し、作陶には真剣に向き合ってきた坂さん。抹茶碗を作るからには、まずお茶に関する工芸や技術が集中している京都で専門的に学びたいと、京都芸術大学(旧・京都造形芸術大学)の陶芸コースを選択した。その後、京都府立陶工高等技術専門校でろくろの技術を1年、産業技術研究所で2年間、焼物の原料を科学的に分析する研究を続け、2013年に萩へ帰郷した。
母である十三世の背中
坂さんが京都で修行している間、母・純子さんが、十三世を襲名。2011年のことだった。

しかし、程なくして純子さんが急逝してしまう。帰郷後、十三世としての母と過ごした期間はわずか1年半。その仕事をじっくりと見て学ぶ時間などなかったし、当時まだ26歳だった悠太さんにとって、たとえ空位になろうと現状の経験値ですぐに宗家を襲名することはできなかった。そこで、しばらくは陶芸家·坂悠太として活動し、その後、2021年にいよいよ十四世を襲名。当初は先々代の頃から坂窯を支えてきた職人たちに、家内の年中行事など、基本の“き“”から教えを乞い、作陶に励んだ。
陶芸家·坂悠太として。宗家当主として
襲名以前、陶芸家·坂悠太として活動していた頃から作品への評価は高く、多くの展覧会で入選を果たしている。
大学時代に学んだオブジェやコンセプチュアルな現代作品にも目を向けており、構図を楽しめる頸(くび)や重心を低くした花器、口の細長い一輪差しなど、萩焼の新たな魅力も提案。伝統に囚われずコーヒーカップなど、新たなジャンルの開拓にも意欲的に取り組んできた。

その一方で、伝統の抹茶椀は、忠実に蹴ろくろで一つひとつ制作する。できるだけ時間と手数を少なくして、土本来の風合いがしっかり残るよう心掛けている。牛へらで美しく成形する際も、指筋や手の跡をなるべく残したいので、あえてバランスを崩し、味が残る作品を意識している。
こうして、新しいアイディアと守り継ぐ伝統技法を掛け合わせた制作が悠太さんの作品の魅力。
口造りと呼ばれる飲み口部分に、高さの切り替えを施した筆洗型(ひっせんがた)抹茶椀は、伝統的な萩焼の基本に、別種の高麗茶碗の形式を融合させている。涼しく縁にうっすらとかかる白釉は、抹茶椀に馴染みがなくても品があり美しく、口に運びたくなる。 高台部分も、土の本来の力強さを強調する「土見せ高台」という、伝統製法も取り入れている。
時に、茶道の専門家から具体的なアドバイスを受け作陶に活かすこともある。最近では、従来1つの盆を回して使うお茶菓子受けだが、近年の新しい生活様式を意識し、個々で使える小ぶりの茶菓子受け「めいめい皿」が好評を得た。次世代に向け、萩焼を進化させるアイデアは、本人の人柄もあってか、周囲の支えを借りながら続々と生まれている。
先代たちの作品に共感し対話する

悠太さんは、亡き母の作品を真似るだけではなく、伯父である十二世や祖父の十一世、時にはもっと前の代まで溯り、制作の工夫や表現の意図そのものを感じとりたいと考えている。大切な作品を後世に残し続けてくれているからこそ、その背景や真意を汲み、再解釈を加えた表現ができる。これこそが十四代にわたって伝統を守り繫いできた宗家の最大の強みであり、これからも後世に繋いでいきたい原動力だ。

現在は数年かけて、十四世としての作品を作り貯め、個展の開催に向けた準備を精力的に行っている悠太さん。萩焼の基本を抑えながら、新たなチャレンジや表現の工夫を行ったり、時には使う側の視点として茶の湯に知見のある人たちからの声に耳を傾け、繊細な登り窯の窯焚きの技術を探求し続ける。宗家だからこそ、伝統を重んじるばかりでなく、十四世として蓄積したナレッジやノウハウを、先の十五世、十六世となる若者たちに繋ぎ、進化や変化をさせていくことで萩焼の未来を作る。人口減少や古典文化離れもあり、先細っていく茶文化。それを“守る”だけでなく、世界へ“発信”し広げることが萩焼の発展にとって最も重要だと考えている。
最近では茶文化に興味を持ち、わざわざ海外から見学にくる人も増えた。そんな環境を目の当たりにした悠太さん。語らずとも世界中の人が強烈に感動してくれる、そんな作品を作っていきたいと話す。











