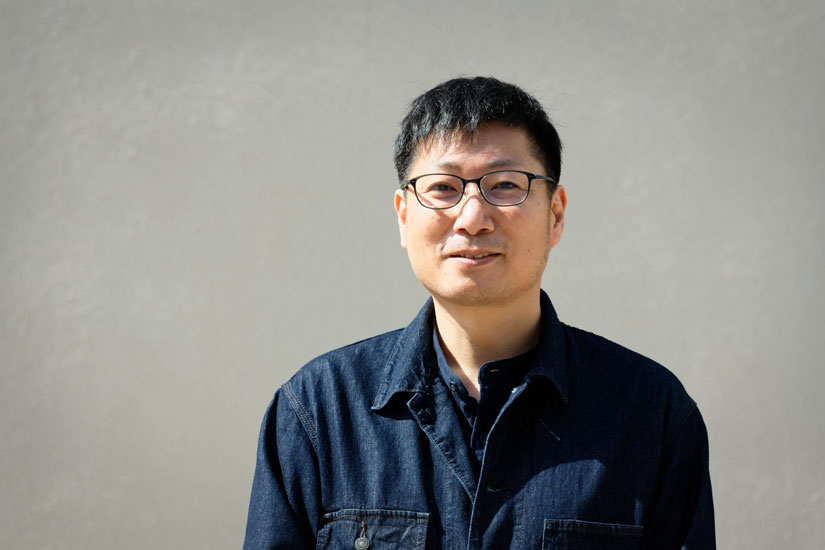富山県にある金工の町・高岡で生まれ育ち、そのルーツは加賀藩主・前田利長に仕えた鋳物師(いものし)。3代目畠春斎(はたしゅんさい)として現代解釈を加えた茶釜づくりを行う。伝統を守りながらも、あえて定石を外し、今の暮らしになじむ茶の湯を提案する。根底にあるのは「多くの人にお茶を楽しんでほしい」という思いだけ。
伝統を守る。恐れずに挑戦する覚悟

高岡城跡から歩いて30分ほどにある金屋町は、高岡銅器産業の中心として栄えてきた場所。溶けた金属を型に流し込んで成型する「鋳物(いもの)」や、金属を使って工芸品をつくる「金工(きんこう)」を手掛ける店が軒を連ねます。
その町で、茶の湯で使われる茶釜を製造する家に生まれたのが畠さん。幼い頃から祖父や父の仕事ぶりをそばで見て育ちました。その家系は、加賀藩2代目藩主・前田利長が高岡に居城した際に、金屋町に移住した鋳物師・釜屋彦兵衛(かまやひこべえ)の末裔。2010年に祖父と父が代々名乗ってきた「畠春斎」を襲名した。
用いる素材は鉄のみ、感性と美意識が生きる茶釜

伝統を重んじる茶道の世界において、近年では茶釜にステンレス陶器などさまざまな素材が用いられている。そうしたなか、畠さんが使用するのは鉄のみ。代々鋳物を家業としてきた背景もあり、あえて素材を限定し鉄だからこそできる表現を追求。「茶室の中で際立つ、鉄ならではの存在感を示していきたいですね」と力強く語る。
この潔い選択が、新たな挑戦を後押しする。制約こそイノベーションの源。ひたむきに鉄と向き合い、3代目畠春斎としての歩みを止めない。
ここ最近の作品は、なめらかな質感と親しみやすさ、そしてどこか凛としたスタイリッシュさを兼ね備えている。鉄の多彩な表情を軽やかに引き出しているようだ。
見て、触れて、感じて。常にセンスを磨く

作品づくりで大事にしているのは、さまざまなものを見て、触れて、感性を養うことだそう。茶釜はいうまでもなく、茶道道具や他の美術工芸品などから日々インスピレーションを得て、価値観のアップデートをしている畠さん。ときには遠方まで足を運び、作り手と語らいながら学びを深めることも。
また、祖父や父の作品を振り返ることもそのひとつ。自身の作品と見比べ、違いを自問自答し続ける。年代やジャンルを問わず多様なものに触れ、作品に少しずつ昇華させる。釜師としての矜持を胸に、毎日が試行錯誤の連続だ。
コラボレーションで広げる新スタイル

日本人の精神と美意識が詰まった茶道。なかでも茶会は、大切な人と過ごす時間を豊かにする場として長く親しまれてきた。しかし文化庁の調査によると、茶道人口は1990年代の600万人をピークに減少し、現在は180万人以下という。
この現状を受け、畠さんは釜づくりに取り組む傍ら、茶道の魅力を広げる活動にも積極的だ。「格式が高くて難しそう」というイメージを払拭すべく、他の作り手と協力してさまざまなイベントを企画。ターゲットは茶道離れが進む若い人たち。興味を持つきっかけづくりを模索する。その原動力は、「多くの人にお茶を楽しんでほしい」という思いだけ。
茶道の魅力は、お茶を味わうことはさることながら、一期一会の交流ができること。茶席で掛け軸や工芸品を眺めたり、茶室の外に広がる景色を愛でたり、時間を共有することで心が満たされる。
最近では、富山の人気木作家「Shimoo Design」や現代アーティストであり造形作家のミヤケマイとの共創を実施。伝統を大切にしながら現代に即したアレンジを提案する。伝統品だから価値がある”ではなく、”本質的に魅力を感じられる”クリエーションに勤しんでいる。
茶会をより魅力的に。決して目立たず、世界観を表現する

畠さんの茶釜が放つ独自の存在感。それは、造形の美しさに加え、茶釜という道具の“役割”を深く理解しているからこそ生まれるものだ。茶会では、亭主が来客にあわせて調度品を並べる。それぞれがバランスよく存在することで、亭主は心からのもてなしができる。悪目立ちすると、世界観をガラッと変えてしまうこともある。
「茶釜は、家における柱のようなものだと考えています。奇を衒うものではなく、でもそれでいて気高い存在感も求められます」。
茶釜は茶会の中心に佇み、世界観を支える役割を担っている。個性を宿しながらも、茶会の一部として程よい存在感のある茶釜を製造する畠さんには、作品のオファーが絶えない。
伝統の枠を超え、自由で親しみやすい茶の湯を

歴代の畠春斎も、時代に合わせて製造を行ってきた。初代は戦争体験を通して「生きているうちに良いものを残したい」との信念を持ち、茶釜づくりに傾倒。2代目は初代の教えをもとに、斬新な感覚を取り入れて新風を吹き込んだ。そして、3代目は現代的なエッセンスを加えて、茶釜の新たな魅力を引き出す。
「使う素材は鉄ですが、重厚感だけではない作品を目指しています」と、やわらかな笑顔で語る畠さん。洗練されたデザインを引き立てるなめらかな質感は、あたたかみを感じさせる。茶道に明るくない人でも「素敵だな」と思わず手を伸ばしたくなるような親しみやすさを纏っているかのよう。
重く固いイメージを抱かれがちな鉄だが、実は強さとしなやかさを併せ持ち、熱を加えることで自在に姿を変える素材である。畠さんが行うのは、その特性を十二分に生かした作品づくり。伝統を重んじる世界に新たな作品が加わることで、これまで茶道に縁がなかった人たちの関心をひく一手になりうるだろう。
伝統は、変わりながら続いていく。茶の湯をラフに楽しむ

お茶の作法には、一つひとつに意味がある。それでも、昔は武士の嗜みとされていた茶道が庶民にも普及したように、時代とともに常に変化してきた。
大量生産大量消費の時代は終わり、一人ひとりの要望に寄り添うことが求められる時代。生活様式や価値観の変化に柔軟に形を変えていくことが伝統継承につながる。畠さんの作品には、そうしたクラフトマンシップが深く根付いている。
茶の湯は元来、大切な人と楽しい時間を過ごすためのもの。作法はもちろん大事だが、根底にあるのは相手を思いやり、心からもてなすという気持ち。茶の湯の本質を捉え、若い人たちがよりお茶に親しんでもらうため、畠さんの挑戦は続く。これからもどんな作品を生み出すのか楽しみだ。