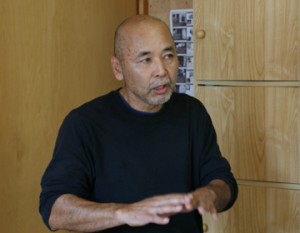名古屋グルメのひとつ「きしめん」は、幅の広さが特徴の麺。うどんよりも薄いのにコシがあり、喉ごしの良さが魅力だが、うどんやそば、ラーメンなどのメジャーな麺類に比べて露出が少ないことも影響し、若者離れは顕著だった。だが最近、名古屋で手打ちうどんの店を営む堀江高広さんによる取り組みで、きしめん業界に新たな動きが見えはじめた。
愛知県の県民食「きしめん」

名古屋めしとして知られている「きしめん」。じつは、名古屋市に限らず、愛知県全域で食べられている県民食だ。ルーツは愛知県刈谷市の名物の平打ちうどん「ひもかわ」といわれており、しっかりとした味付けを好む人が多い愛知県では、つゆの味が染みやすいきしめんがマッチしたのではないかと考えられている。
その特徴は、なんと言っても平打ちの麺。うどんよりも薄いのにコシがあり、喉ごしが良いことと、ジュワっと染み出るつゆが魅力だ。
きしめん、うどん、煮込みの麺の違いとは?

名古屋めしを代表する麺類には、きしめんのほか、味噌煮込みうどんや名古屋うどんがある。どれも同じ“うどん”のように思えるが、それぞれの料理に使用される麺は調理方法や用途に合わせて材料やその配合率が異なり、それに伴って食感もさまざま。
なかでも製麺に最も手間が掛かるのがきしめんだ。きしめんは、大きな特徴である幅の広い麺にするため生地を薄く伸ばすから、一般的なうどんの製麺工程に比べ、二倍以上の時間を要する。また、薄く伸ばすことで生地が広がって麺打ち台を占拠するため、一度に作れる量も限られる。同じ時間、同じ製麺環境で、うどんを10人前作れるとしたら、きしめんは5人前しか作れない。名古屋名物とは言え、その効率の悪さから、きしめんの提供をやめ、うどんだけに切り替える店も増えているそうだ。
先代が開いた麺類食堂から、うどん・きしめん・煮込みの三本柱に

名古屋市で「手打うどん 高砂(たかさご)」を営む堀江さんは、父親が1958年に創業した麺類食堂を受け継いだ。麺類食堂とは、うどんだけではなく、中華そばや定食も提供する町の食堂の総称。父親が亡くなり堀江さんが跡を継いでからは、手打ちにこだわる店として、うどん・きしめん・煮込みうどんを三本柱に店を営んできた。
東京での修業を経て、見よう見まねで技術を習得
高砂でうどん作りを始める前は、東京のとあるそば屋で修業をしたという。毎日ひたすら出前などの下働きを続け、2年後に父の店へ帰ってからは兄弟子のうどん作りを見ながら技を盗み、自分のものにしていった。
「優しいのだけど芯はあるというか、最後にちょっと歯応えがあるような麺を目指している。頭で考えるだけではなく、実際にやってみて技術を身につけ、ようやく理想の麺が安定して作れるようになりました」と堀江さん。
その独自の技術によって作られる手打ち麺が高い評価を受け、今ではミシュランガイドに掲載されるほどの名店になった。
塩水の濃度が高い名古屋のうどん。一晩おいてから伸ばす理由

うどんときしめんの原材料はどちらも小麦粉と塩水。その製造工程もほとんど同じで、生地を打つ段階での伸ばす厚みだけが異なる。ただし名古屋のうどん作りで使われる塩水は、うどん県として有名な香川県などで製麺に使われるものよりも濃度が高い。
季節や天候によっても左右されるため一概にはいえないが、ほかの地域の塩水が濃度10%だとすると名古屋では18~20%ぐらいの塩水を使っている。「濃度が高いと生地が締まります。名古屋は気温の高い地域なので、暑さで麺がだれるのを避けるために塩分濃度を高くして生地を硬くしたのではないでしょうか」と堀江さんは言う。
さらに、名古屋のうどんは「名古屋打ち」と呼ばれる方法で作られる。他地域のうどんとの大きな違いは生地を一晩寝かせること、団子状の生地を指で押し込みながら丸い形に整える「へそ出し(本まるけ)」といわれる工程があることだ。寝かせることでグルテンの形成を一層促進させて粘り気と弾力を、へそ出しによって生地の空気を抜くことで、切れにくく強いコシを生み出す。これらのひと手間が、名古屋うどんの特徴を作り出している。
生地と会話しながらの麺打ち
堀江さんは毎日、うどんやきしめんの麺打ちを行っているが、その作業は同じではない。「今日は湿度が高いから柔らかいよね、などと生地と会話しながら麺を打っています。生地を形成することを僕らは『鍛える』といいますが、むやみやたらに鍛えるのではなく、生地を休ませながら、無理をさせないようにやっています」と堀江さん。夏は締まりのない生地になりやすいためさらに塩分を増やしたり、雨の日は水を減らしたりと、微調整を加えてその日にベストな生地を作り上げているのだ。
きしめんを若い世代に広め、日常食の選択肢に

愛知県民のソウルフードといえるきしめんだが、実は衰退の危機にあるという。先述したとおり、きしめんは他の麺類に比べ作る手間が多い。また、ぐつぐつと煮込まれた味噌煮込みうどんの方が、店側の調理の負担も少なく、観光客へのウケもよい。地元民にとってもわざわざきしめんを食べる機会は多くなく、高砂でも3年ほど前までは、1週間に2〜3食出るか出ないかだった。
だが、きしめん文化を残したいと考えた堀江さんは、カジュアルな店で若い世代にきしめんのおいしさを伝えることを決心。麺の機械打ちや冷凍技術を取り入れて、気軽に立ち寄れる店「星が丘製麺所」を2021年にオープンさせた。
「星が丘製麺所」がある星が丘テラスはアパレルショップやカフェなどが並び、多くの若い世代が行き交う場所。手打ちにこだわる高砂とは製法も立地も逆方向のお店に思えるが、その真意を堀江さんはこう語る。「手打ちで麺を仕込むとコストがかかり、大量生産もできません。でも若い人に、カレーやラーメンと同じような感覚できしめんを食べてもらいたくて。手打ちの技術を落とし込んだ機械打ちなら、味に遜色なく、気軽に食べてもらえると思い、すぐに製麺せずに一旦生地を寝かすなど、試行錯誤を繰り返し、機械打ち史上最良の品質を目指して開発に励みました」。
星が丘製麺所のオープンから1年間でオーダーされたきしめんは約10万食。さらに、きしめんのおいしさを知った客が高砂へも足を運ぶようになったのだ。客層もこれまでと異なり、女子高生のグループが来店したり、ママ友がランチでやってきたり、塾へ行く前の子どもたちが来店したりと、狙い以上の結果となった。
東海エリアから全国、海外へ
星が丘製麺所の成功により、同業他社からも喜びの声が届いているという。「他店のきしめんも味わってみたい」と、昔ながらのうどん店に若年世代の来店が増えたのだ。だが、堀江さんは一時的なブームで終わらせないためにもフランチャイズ展開を進めるなど、精力的にきしめんを広める活動を継続している。
「現在、星が丘製麺所は愛知県と大阪府に店舗がありますが、ゆくゆくは北海道から沖縄まできしめんの文化を広げていきたい。将来は海外にきしめんファンを増やしたいですね」と堀江さん。いつの日か、きしめんがうどんやそば、ラーメンのように日本における麺食のスタンダードとなり、世界中に広まっていく。そんな未来を想像しながら、名古屋のいち商店からスタートしたうどん店が幅広いニーズの掘り起こしを図るべく、新たな切り口できしめんの魅力を発信し続けている。