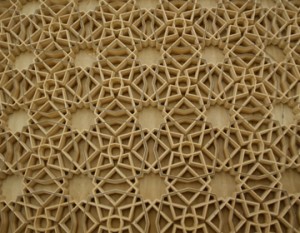時代を超えて愛されるアンティーク家具
1944年創業の松本市内にある老舗家具メーカーに向かう。松本民芸家具の中央民芸ショールームで、創設者の池田三四郎の孫、常務取締役 池田素民さんが出迎えてくれた。ここで造られる松本民芸家具は、欧米のアンティーク家具に学んだ和洋を織り交ぜたデザインと時代を超えて使える堅牢な造りが魅力。全国あまたのファンが支持している。「松本民芸館の丸山太郎さんと祖父が同級生で、それがきっかけとなり民芸という世界に私たちも入った」と池田さんは話してくれた。

自我がなくなると自然に美しくなる家具
松本は400年以上も家具の産地だが、以前、その伝統は消えようとしていた。「柳(宗悦)さんに伝統は一度火が消えると二度と元には戻らない、と言われ一念発起で家具店を始めた」と池田さん。長く使える「決して飽きることのないもの」をつくること、それには「造り手の自我を削いでいく。自我がなくなると自然な美しさが出てくる。主張があるものはいずれ飽きられる。空気のようであり絶対的に美しい存在であることだ」。中田が一番のヒット家具を伺うと、「#44ウインザーチェア」だと教えてくれた。イギリスの庶民文化から生まれた椅子で「この椅子の力学構造を超えられる椅子が出てこないほど、完成度が高い」と池田さんは話した。

木取り職人、組立職人、塗装職人が分業する家具作り
近くにある家具工場に案内していただく。家具作りは木取り職人、組立職人、塗装職人が分業して完成させる。分業のほうが「合理的にムダなく材料を使える」という。誰がつくったのかが分かるように造った職人の名前を一文字彫るのが習わしだ。最終工程の塗装場では、塗装職人が丁寧に椅子にニスを塗っていた。手刷毛で馴染ませながら、12工程もかけながら仕上げる。こうすることで使いこんでいった時に違いが生まれてくる。完成間近の椅子を見ながら、「松本民芸家具といえばこの重厚感のある濃い色だ」と中田。「昔の民家では囲炉裏でいぶされた柱を毎日磨いていた。その色は日本人のアイデンティティのなかに刻まれた色だ」と三四郎氏が決めたそうだ。